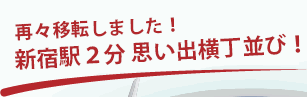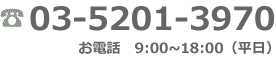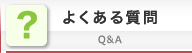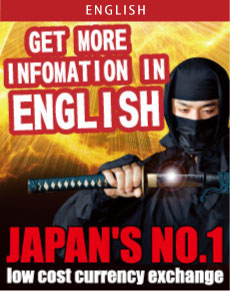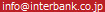0908 チケットショップ入社
2006年末、成田空港駐車場で両替ショップを開業するという目論みは脆くも崩れ去った。
私は大変恩のある仕入先のチケットショップの社長に、行動している時から全て成田出店の進捗のことなどを報告していた。そしてそれが破談したことも全て包み隠さずに話しをしていた。たまに仕入れに行くときには必ず声をかけて、近況報告や参考になりそうな資料や文献などを持って行くようにしていたので社長もずいぶん気に入ってくれている様子であった。立場的には一取引相手だが、親身になって商売の助言や経験則などを教えてくれていた。私にとっては最大の取引先で、しかも厚遇扱いで仕入れをしてもらっているので最も大事な人脈の一人であると意識し、真意で感謝をしていた。
その社長からある日、君に話があるので約束の時間に来るようにと言われた。直接お呼びがかかることなど無かったので何か特別なことがあるのだろうと、何も動きが取れなかった私は些細な期待をし、言われた日時に喫茶店でお会いした。社長の話はこうだった。彼の会社は順当な利益を計上しているが、将来を見据えれば金券業の展望を憂慮しており、他の業態にも積極的に進出をしていく戦略があるので、そのことで彼自身の手となり足となり事業を手伝って欲しいということだった。毎月一定の金額を報酬として出すので、私の会社の売り上げとして上げればいいし今の会社を廃業することもない。本業の両替事業も続けても良いという提案内容だった。
苦戦している私を見かねたのだろうか、そして彼の意中にはそれなりの人材を引き込む良い機会とも思ったのかもしれない、現にその会社はほとんどがアルバイトや契約社員で構成されており、戦略的な役職者のいない社長1人の手腕と頭脳で築き上げたワンマン企業であったのだ。私は悩んだ、そして内心忸怩たる思いを感じずに入られなかった。ベテランの商売人であるこの海千山千の社長から助け船を出してもらっているとはいえ、すでに自分の窮状を察せられもはや他人に介在される余地があるほどの身であることを甘受しなければならない不甲斐なさ。それでも現実を受け入れなければならない、実際問題このままでは資金が底をついてしまうのは時間の問題だった。商売を諦めるわけではない。社長の会社も彼が高齢ということもあって、インターネットでの集客や外部への営業活動といったことの私が経験してきた仕事は大いに重宝されるだろうし、むしろ貢献できる自信もある。実質的には給料のような形で定期的にお金を頂戴するが、成果を上げればうんと見返りの高い報酬を出すことは実績主義の民間企業として当然であるという話もいただいた。この話は私に発注されたプロジェクトのオファーであり、企業間の取引である。そう自分の中で納得して、話が終わるころには頭の中での決断はほぼ固まっていた。なによりも、経済的な問題が解決されることがすこぶる絶対的な安堵感をもたらしてくれた。逃げ道を選んだ、そうだろうか。誰に恥じることがあるというのか。私の会社などこの世に五万とある事業体のうちの極小さな一つ、しかも吹けば飛ぶような、飛んでいなくなってしまっても誰も困らない、気付きもしないじゃないか。そんな米粒のような分際で今さら初心貫徹のプライドを振りかざすのか。根性論じゃないんだ、また体勢を立て直し軌道修正したらいい。
捨てる神あれば拾う神ありだ。話し合いの前とは違う清々しい気分で幾分軽やかに、先に待ち受けている未来に希望的観測をこめ地面を踏みしめながら帰宅した。志を蔑ろにしている自分にたっぷりの言い訳をして。
一週間後に返事を聞かせてくれとのことだったので、とりあえず何人かの人に相談をした。私の内情を知ってか知らずか、何故か反対する意見が多かった。その中でも特に、起業のカリスマといわれ、多くの起業家に慕われて広範な活動をしているプロの相談相手の方に本気で幻滅され徹底的に批判された。そこまで大げさにならなくてもいいじゃないだろうか、冗談なのか本気なのか、「起業家でもなんでもねぇよ。」と吐いて捨てられ、いつもは優しい彼の表情が怒りと悲しみの歯がゆさで曇っていたように思えた。私はそのことを少しは気にかけながら、口角泡を飛ばしては自論を押し通そうと抵抗し、結局心変わりすることも無かった。救いようの無い分からず屋と思われたであろう。一度決めたら反対は無視し、肯定論にだけ耳を傾ける性格がそのころから幅を利かせていた。
2007年を迎え、新年の仕事初めから晴れて心機一転、チケット屋の実質的社員として事務所に出社し、他のスタッフの社員に顔見世の挨拶と自己紹介をした。しかし、直前まであまり気にとめていなかったのだが、そこにいた社員の人々は私が仕入れで何度も何度も通っていた店で接客をしていた相手で、つまり顔見知りの面々だったのだ。面識があるから歓迎を受けるのが通常かもしれないがあまりにも私は店頭での取引を繰り返していたので、有限会社社長である素性も、そして暇さえあれば社長に擦り寄っていく媚売りのゴマすり小男である認識を持たれていたのではないかと思う。「何で客だったこいつがいるわけ・・・」そんな冷たく乾いた視線に内心戸惑ってしまったが、なるべくはつらつと元気に笑顔で挨拶をしたつもりだった。しかし、私が挨拶を終えたあとも一同、一切表情を変えることなく、もちろん拍手など起きようはずもなくその一瞬を察したのか沈黙を打ち消す社長のフォローで朝礼が終わり席に着いた。飛んでもないところに来てしまった、顔から火が出る思いで新人にも関わらず体を丸めてまるで引き際の身辺整理をするかのような気まずい思いで荷物を整理した。
こんなこともあった、昼食時1人で入った定食屋に皆が一緒になって食事をとっていたちょうど目の前に現れてしまい、偶然にも一席だけ空いていたので彼らも気付いてしまったタイミングで「お疲れ様ぁ、ここいいですか。」と無視するわけにもいかずに同席をし、存分の気を遣って話しを振っては不自然にも盛り上げようと努力した。しかしその後事務所に戻ったらさっき食事を共にしたはずの隣の女子は全くこちらを見ようとすることもなく、「●●さん、ホッチキス貸してもらってもいいかな。」と無理に話かけても目を合わさずに、言葉を交わすことも必要最低限という張り詰めた雰囲気になっていた。
また、会社近くの道端で目が合っても会釈もせずに目をそらされたり、ランチで食事をしていて1m前にいるにも関わらず無視されたりと、いくらなんでもそれは無いでしょうよと。信じられずに一体どうなってんだここの教育と環境はと愕然とした。組織としても明らかに世間とずれていた。事務所内は禁煙だったが、喫煙してもよい場所は併設された休憩所兼更衣室だった。しかし、その部屋の上は壁がなく天井が開いており誰かがタバコを吸えばすぐに事務所中が煙くなって、非喫煙者であり嫌煙家の私はとても気分が悪かった。
30歳半ば以降と思われる大の大人が靴のかかとを踏みつけて仕事をしているのには、決定的な人間性の欠如を実感した。しかも社長が挨拶をしないものだがら誰も挨拶を社内でしない。以前努めていた証券会社だったら統括部長や役員が出社すると支店長始め総勢30人余りの社員全員が立ち上がって挨拶をしていたものだ。まるで天皇だった。かつては営業の会社だったから一般の会社と比べたら礼儀礼節、規律に関しては厳しい環境であったと思うが、それにしてもここのそれは会社組織としての最低ラインをはるかに下回っている。他人の会社とはいえ、業績を上げるには個々の社員の意識改革をして現状を変えねばこのままここにいたら自分にとっても悪影響が出かねないしそもそも仕事が出来ない。そのこと諸々を含めて箇条書きにして社長に社員に対しての心得として改善要求書を提示し改革を訴えたが実際にそれが受け入れられることはなかった。人様の会社、しかも同族である中小企業だから私が口を挟む権利など無いのだろうが、社長の現場感覚のズレと是正に踏み切らない姿勢に失望しながらも耐える日々を送ることになる。
まるで動物園だった。社内での責任者が社長だけなので、社長が居るときには皆黙って個々の仕事をしているフリをしているのだが、帰った後には机に座って女子特有のお喋りやネットサーフィン、社長の悪口を大声で言い合ったりとやりたい放題なのだ。しかもそれは社長の娘である名ばかり管理者が率先していたので、私は注意する権限も無く1人孤立して自分の作業を黙々としているしかなかった。世の中に存在する会社も所違えばこんなにも歴然とした差があるのかとまったく呆れて、彼らの将来や教育の無さを不憫にすら思えた。そんな会社に在籍するしかなかった私は何をしていたかというと、社長に頼まれた仕事をこなしていたのだが、主に参入した高速バスの集客について奔走していた。ネットでの広告を提案したり、旅行社に協業を持ちかけ顧客を紹介してもらうというような営業活動だった。うまくいったものもあれば効果なく終わったものもあり、あまりうだつの上がる状況ではなかった。その間でも自身の本業の外貨両替の注文が入ったりすると、席をはずしてトイレや階段の踊り場で顧客と連絡をとり、外回りと称して自社のレンタルオフィスの事務所へ出向き取引を行っていた。ネットからの注文はパソコン上から対応できるので難なくこなせたが、外貨を仕入れに今在籍している会社のお店に出向くのが段々と気まずく嫌になっていった。それでも全体的に注文件数の絶対数が少なかったので、チケット会社からの報酬25万円程度を自社の赤字に埋めあわせをして、いくらか手元に残るような状態を続けていた。ひどく体たらくな環境に身を置いていたが、そこで特に頑張ることもなく、段々と馴れ合いになっていき自社の再起へ向け努力もせずに相変わらず本業の目が出る気配もなかった。
自分の会社の行く末は不明、それでいてけじめをつけることの収集もつけられなくなっていた。実質雇われているようなサラリーマン形式で、チケット会社から毎月お金がもらえるのをいいことにプライベートを復活させたり、欲を出して金融商品に手を出したりと、事業に成功してやるという高く掲げた志は地に落ちていた。
毎日機械的に出社をしても数字を求められたり、細かい指示があるわけではない仕事だったので、時間が過ぎ去ること、ひいては社長が帰るのを待つような自分も他の周りの連中と大して変わらない精神構造になっていた。まさに朱に交われば赤くなるというやつである。